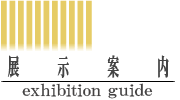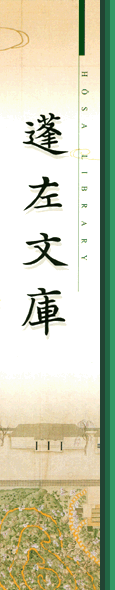
 重要文化財 刀 銘 本作長義・・・(以下58字略)
重要文化財 刀 銘 本作長義・・・(以下58字略)
2025年6月14日(土曜日)から9月7日(日曜日)
徳川美術館・蓬左文庫開館90周年記念
夏季特別展
「時をかける名刀」
- ■会場
- 徳川美術館本館展示室/蓬左文庫展示室
- 大名・尾張徳川家に伝来した名刀のなかには、複数の天下人の手を渡り、戦乱をくぐり抜けてきたというような輝かしいエピソードを持つ刀剣や、戦功や慶事の祝儀に贈られたという縁起の良いエピソードを持つ刀剣が数多くあります。刀剣それぞれの価値・重要性は、こうしたエピソードによって高められていたといっても良いでしょう。
本展覧会では徳川美術館の所蔵刀のうち国宝・重要文化財、また古くから名高い名物刀剣を軸として、歴史に名を馳せた武将や大名ら所縁の名刀を展示し、歴史的背景の面白さと、刀剣そのものの美しさの両側面から、刀剣の奥深い魅力を紹介します。
展示の詳細案内
葵紋散螺鈿黄金造太刀拵
(あおいもんちらしらでんこがねづくりたちごしらえ)

「小太刀 銘 吉用(よしもち)」(No.125)に附属する太刀拵です。刀身・拵ともに、尾張家初代義直(よしなお)が浅野幸長(よしなが)の娘・春姫(はるひめ)と婚約した際、幸長の弟で広島浅野家初代の長晟(ながあきら)より贈られました。梨子地の鞘には葵紋が蒔絵(まきえ)・螺鈿(らでん)・金貝(かながい)により散らされ、金・銀製の総金具が附属しています。金工・漆工の技法を凝らした豪華な作りで、江戸時代初期における有力大名家同士の婚礼の華麗さと大名家の品格を象徴しています。
浅野長晟(広島浅野家初代)・徳川義直(尾張家初代)所用
江戸時代 17世紀
花生椿水仙菊図三所物 銘 後藤顕乗(花押)
(はないけつばきすいせんきくずみところもの
めい ごとうけんじょう(かおう))

赤銅魚々子地に金銀色絵で、花生に生けた椿や水仙などを表す清楚な三所物です。魚々子(ななこ)とは、文様の下の部分(地(じ))に鏨(たがね)で打つ彫金技法の1つで、魚の卵のような見た目から魚々子と呼ばれます。かつて「刀 金象嵌銘 正宗磨上 本阿弥(花押) 名物 池田正宗」(No.93)の拵(こしらえ)に附属していましたが、その後取り替えられて、三所物として保管されました。
後藤顕乗(後藤家7代)作
江戸時代 17世紀
刀 無銘 一文字 名物 南泉一文字
(かたな むめい いちもんじ めいぶつ なんせんいちもんじ)

豊臣秀吉の所持した名刀で、慶長16年(1611)、政治的緊張が高まるなか京・二条城で豊臣秀頼が徳川家康と会見した折に、家康に贈られました。家康の歿後は尾張家初代義直(よしなお)へ譲られ、尾張家では足利将軍家から継承された品とみなされ、為政者としての正統性を語る品として代々受け継がれていきました。備前国(現・岡山県)一文字派(いちもんじは)による刀で、多様な変化をみせる大房の重花丁子乱(じゅうかちょうじみだれ)を焼いた絢爛豪華な1口です。
伝足利将軍家・豊臣秀吉・秀頼・徳川家康・徳川義直(尾張家初代)所持
駿府御分物 鎌倉時代 13世紀
重要文化財
太刀 銘 長光 名物 津田遠江長光
(たち めい ながみつ めいぶつ つだとおとうみながみつ)

天正10年(1582)の本能寺の変の直後、明智光秀が安土城から奪取した織田信長の所持刀で、家老の津田遠江守重久(しげひさ)に与えたと伝わります。江戸時代には将軍家と、名門大名家である加賀前田家・尾張家との栄えある贈答に用いられました。備前国長船派(おさふねは)の長光(ながみつ)による太刀で、磨上げられているものの、腰反りで均整のとれた太刀姿です。刃文は豪華絢爛な丁子乱(ちょうじみだれ)で、淡い乱映(みだれうつり)が鎬(しのぎ)を超えた高い位置にまで現れ、一層華やかです。
長船長光作
織田信長・明智光秀・津田重久・前田利長(加賀前田家2代)・綱紀(同家5代)・
徳川綱吉(5代将軍)・家宣(6代将軍)・徳川吉通(尾張家4代)所持
鎌倉時代 13世紀 国宝
刀 銘 本作長義 天正十八年庚刁五月三日ニ九州日向住国広銘打 長尾新五郎平朝臣顕長所持 天正十四年七月廿一日小田原参府之時従 屋形様被下置也
(かたな めい ほんさくちょうぎ てんしょうじゅうはちねんかのえとらごがつみっかきゅうしゅうひゅうがじゅうくにひろめいうつ ながおしんごろうたいらのあそんあきながしょじ てんしょうじゅうよねんしちがつにじゅういちにち おだわらさんぷのとき やかたさまよりくだしおかるなり)

長尾顕長(あきなが)が、天正14年(1586)に北条氏直(うじなお)から拝領した刀です。顕長は同18年の小田原合戦では氏直に従って籠城しますが、領国の足利周辺が豊臣方に制圧された時期にあたる5月3日、北条方の武将として決戦への覚悟を示すように本刀に銘を切らせます。銘文から歴史的な経緯が判明する珍しい例です。備前国長船派の刀工・長義(ながよし)による、身幅が広く切先(きっさき)の大きい堂々とした姿の太刀です。多彩に変化する箱型の大互の目乱(おおぐのめみだれ)が華麗な1口です。
長船長義作
北条氏直・長尾顕長・徳川綱誠(尾張家3代)所持
南北朝時代 14世紀 重要文化財
脇指 無銘 貞宗 名物 物吉貞宗
(わきざし むめい さだむね めいぶつ ものよしさだむね)

徳川家康から尾張家初代義直(よしなお)に譲られた1口で、尾張家では万事吉祥を意味する「物吉」と名付けられて家宝とされました。江戸時代中期には、三河時代の家康に戦勝をもたらした縁起の良い刀剣という由緒が語られるようになり、家康の神威を借りて尾張家当主の権威をさらに高めようとしていたことが窺えます。相模国の貞宗の傑作で、地鉄(じがね)は明るく地沸(じにえ)がつき、刃文は湾(のたれ)を基調として特に切先(きっさき)付近で激しい変化をみせています。
相州貞宗作
豊臣秀吉・徳川家康・徳川義直(尾張家初代)所持
南北朝時代 14世紀 重要文化財
PDFファイルをご覧になるにはアクロバットリーダーが必要です。
左のアイコンをクリックしてソフトをダウンロード(無償)してください。
Acrobat及びAcrobatロゴは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。
本文終了